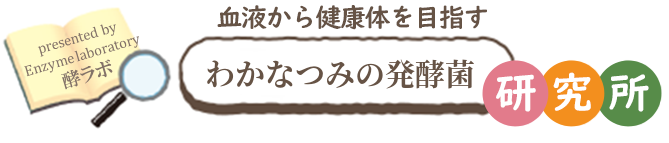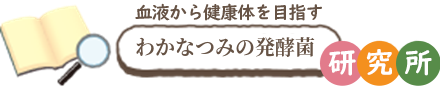健康・長生きのために飲む
「わかなつみの発酵菌」の効果を徹底分析
痛風の予防法・酵素の効果と研究結果
痛風とは
痛風とは、血液中で結晶化した尿酸が原因で、関節に激しい痛みをもたらす病状のこと。ある日突然、発作のように痛みが発生し、その後1週間から10日程度、痛みが続きます。
痛風を誘発する直接的な原因は、血液中の尿酸値の上昇。尿酸は、プリン体という物質が原料となって作られます。
尿酸の原料はプリン体
痛風を誘発する尿酸は、食べ物に含まれるプリン体という物質から作られます。プリン体は、おおむね細胞の数に比例して含まれる物質。レバー、イワシ、白子、アンキモ、カツオ、イワシなどに多く含まれていることが知られています。
痛風は再発する
痛風発作は1週間少々で治まりますが、一度発作を起こした場合、その後の生活習慣などに注意して過ごさない限り、発作は1年後くらいに再発します。再発後も生活習慣を改めなければ、発作の間隔が徐々に短縮。やがて慢性痛風という重篤な状態にいたることもあります。
痛風の原因
激痛のもとになる尿酸は、プリン体といわれる物質が原料で、次のような3つの方法で作り出されます。
- 食べる食品にプリン体が含まれており、食事によって体内のプリン体が増える
- 体内の細胞の核酸にプリン体が含まれており、新陳代謝により古い細胞が分解されるとプリン体が出てくる
- 急激にエネルギーを使うとプリン体が生み出される
出典:オムロン公式HP「vol.6 痛風の原因とその予防法」
https://www.healthcare.omron.co.jp/resource/column/topics/6.html
冒頭でも触れたとおり、痛風の原因は血液中に含まれる尿酸。男性の場合は4.0~6.5mg/dl、女性の場合は3.0~5.0mg/dlの尿酸値であれば正常です。7.0mg/dlを超えると「高尿酸血症」と診断され、この「高尿酸血症」の状態が長く続くと、やがて血液中で結晶化した尿酸が関節に蓄積し、痛風発作へといたることがあります。常に尿酸値が8.5mg/dlを超えている人は、いつ痛風発作が生じても不思議ではありません。
尿酸を作り出す原料となる物質がプリン体です。尿酸値が高めの方は、痛風を予防するために、プリン体を多く含む食材の摂取を控えることが大切です。
なお昨今、「プリン体カット」を謳うアルコール飲料が多数販売されていますが、そもそもアルコール飲料に含まれるプリン体は微量です。ただし、アルコール自体が尿酸の排出機能を低下させることから、痛風を予防するためにはアルコールの過剰摂取を控えることが大切です。
遺伝が強く関与しているという説もあり
痛風の原因について、プリン体の摂取量過多による尿酸値とは別に、遺伝的な要素が強いと指摘する研究報告もあります(※1)。
※1:東京大学「痛風遺伝子の発見」
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/vcms_lf/r20091105084732.pdf
痛風の代表的な合併症
痛風の主な合併症には、以下の3つがあります。
慢性腎臓病
慢性腎臓病とは、「何らかの原因」による腎臓障害が3ヶ月以上続いている状態のこと。自覚症状が現れることはほとんどなく、尿検査や腎機能検査などで発見されることが大半です。
慢性腎臓病を誘発する「何らかの原因」の一つが、高尿酸血症。体内に生じた結晶が腎臓に溜まることにより、腎機能を低下させて慢性腎臓病を招くとされています。慢性腎臓病は、痛風と併発することのある代表的な合併症です。
虚血性心疾患
痛風患者や高尿酸血症と診断された患者は、一般的な人に比べ、虚血性心疾患を発症するリスクが高くなると言われています。
虚血性心疾患とは、狭心症や心筋梗塞など、心臓の冠動脈の流れが悪くなる病気。心筋梗塞はもとより狭心症もまた、死を招きかねない恐ろしい病気です。
なお、高尿酸値が虚血性心疾患を招くメカニズムについては、現状、分かっていません。メカニズムは分かっていませんが、統計上、関連していることは確かとされています。
脳血管障害
尿酸値の高い方は、脳血管障害を合併するリスクが高くなるとされています。
脳血管障害とは、脳梗塞やくも膜下出血など、脳内の血管に生じた異常の総称。軽度の脳血管障害であれば治療によって完治することもありますが、重度の脳血管生涯の場合には、発症からほどなく死にいたることもあります。
虚血性心疾患と同様、高尿酸値が脳血管障害を誘発するメカニズムは分かっていません。ただし、統計上、両者に関連があることは確かなようです。
痛風のリスクを高める要素
痛風のリスクを高める主な要因として、プリン体のほかに指摘されている以下3つを確認してみましょう。
ストレス
ストレスが尿酸値を上げることは、かねてから知られていました。仕事におけるプレゼンテーションの当日や、大切な出張の際など、精神的ストレスのかかるタイミングで痛風発作を起こしたという例は、身近でも聞かれることでしょう。
鹿児島大学医学部では、医局主催のゴルフコンペの前後で、参加者の尿酸値を測定しました。するとゴルフコンペ前日から尿酸値が上昇している医局員が多いことが判明。精神的な緊張や高揚感などが、尿酸値を高めることが示唆されました。
また平成29年、名古屋大学を中心とする研究グループは、マウスを使った実験を通じて、ストレスが尿酸値を高めることを突き止めています(※2)。
※2:名古屋大学プレスリリース「ストレスが高尿酸血症の発症に関与するメカニズムを解明」
https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/research/pdf/scientific%20reports_20170428.pdf
飲酒
先に触れた通り、アルコール飲料に含まれるプリン体は、ごく微量です。「ビールにはプリン体が多い」との俗説がありますが、これは他のアルコール飲料と比較したときの話。ビールに含まれるプリン体の量は、肉類などの一般的な食材に比べれば極めて微量です。
一方でプリン体とは別に、アルコールの作用そのものが尿酸値を上昇させることが指摘されています。アルコールの代謝の過程で尿酸が作られる、というメカニズムによるものです。
尿酸値が気になる方は、プリン体の量に注意してアルコール飲料を選ぶのではなく、そもそもアルコールの摂取量を減らすことを心がけましょう。
肥満
肥満と高尿酸血症との関連は、国内外における研究機関から数多く報告されています。両者には強い関連性があると考えて間違いありません。
肥満が尿酸値を上げる最大の理由が、過食です。尿酸の原料となるプリン体は、ほぼすべての食材に含まれているため、過食の傾向が強い人ほど、プリン体の摂取量も多いことになります。
加えて肥満傾向の方は、肉やレバーなど、プリン体の含有比率の高い食材を好む傾向もあります。これら食材の好みの傾向も、肥満と尿酸値を関連付ける要素の一つと言えるでしょう。
なお肥満かつ尿酸値の高い方は、減量することにより尿酸値が正常化することが多いとされています。痛風予防のために、ダイエットや運動習慣を意識するようにしましょう。
わかなつみの発酵菌の痛風へ期待できる働き
わかなつみの発酵菌の尿酸低下作用(痛風の抑制効果)を検証する第三者機関による実験では、わかなつみの発酵菌を与えたマウスは、与えてないマウスに比べて30%以上も血中尿酸値が低い、という結果が出ています。
痛風と酵素の関係
痛風の原因となる尿酸は、体内でエネルギーを消費したときや、細胞が新陳代謝する際などに排出される老廃物。またレバー類や魚卵などのプリン体からも尿酸は発生します。
体内に尿酸が溜まり過ぎないよう、プリン体の多い食品を摂取しないよう制限したり、尿として体外へ排出されるようこまめに水分を摂るなど、対策が必要です。
そこで痛風の改善に効果が高い酵素を摂取することも、有効だと言われています。酵素は血液中の老廃物の排出を促して、血液をサポートする効果が期待でき、尿酸の排出にも積極的に作用します。
痛風を改善させるために、日ごろの生活に酵素を取り入れることを検討されている方は、ぜひ血管サポート力の高い酵素を選んでみてはいかがでしょうか。