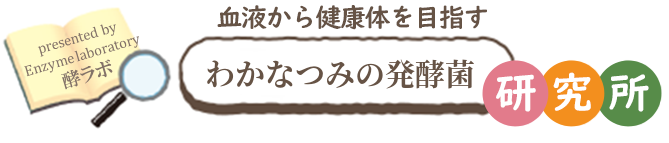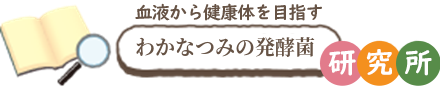健康・長生きのために飲む
「わかなつみの発酵菌」の効果を徹底分析
狭心症の予防法・酵素の効果と研究結果
狭心症とは
狭心症とは、何らかの理由で心臓の表面にある冠動脈のトンネルが狭くなり、血液が十分に運ばれなくなることから生じる発作。発作時には胸や腕、肩などに痛みを自覚しますが、発作が治まると痛みは消滅します。
狭心症の種類は、大きく分けて2つ。労作性狭心症と安静時狭心症です。
労作性狭心症
体を動かしているときに発症する狭心症。スポーツをやっているときや階段を上っているときなど、普段よりも心筋が血液を必要としている状態のときに好発します。
動脈硬化などによって冠動脈が狭くなってしまっている人は、急な激しいスポーツなどに注意しなければなりません。
安静時狭心症
体を安静にしているときに生じる狭心症。就寝中や起床前後などに好発するタイプです。
安静時狭心症の原因の大半が、冠動脈が痙攣して収縮する冠攣縮(かんれんしゅく)という症状。冠攣縮が生じる原因には不明な点が多いのですが、一説では遺伝的要因や動脈硬化が指摘されています。
狭心症の原因
何らかの原因で血管が狭くなり、細胞の血液(酸 素)の需要に対し、その供給が不足して起こる病気を 「虚血性の疾患」といいます(虚血とは、血液が少ない という意味です)。虚血が心筋に起きる病気を「虚血性心疾患」といい、その代表が「狭心症」と「心筋梗塞」 です。虚血性心疾患の多くは、動脈硬化から起こります。かつて日本では少なかった虚血性心疾患も、食生活の欧米化などから、年々増加しています。
出典:一般社団法人日本臨床内科学会「狭心症」
http://www.japha.jp/doc/byoki/008.pdf
狭心症の直接的な原因は、心臓の血管が狭くなること。心臓の血管が狭くなることで、心臓が必要とする血液が十分に供給されなくなる状態のことを、狭心症と言います。また、狭心症がさらに悪化し、心臓に血液がほとんど供給されなくなる状態のことを、心筋梗塞と言います。
上の引用でも触れられている通り、狭心症の原因の多くが動脈硬化。生活習慣等の原因で血管が固くなったり、血管が狭くなったりする症状が動脈硬化です。食生活の欧米化などの影響で、日本では動脈硬化の患者が徐々に増加。結果として、狭心症や心筋梗塞の患者の数も、少しずつではありますが増加しています。
動脈硬化は、加齢とともに避けられない症状の一つではありますが、一方で生活習慣が大きく影響している症状としても知られます。暴飲暴食や運動不足、塩分過多や喫煙などによる高血圧が、動脈硬化の誘発要因として知られているため、動脈硬化の予防のためには、生活習慣を見直すことが非常に大切です。
狭心症の代表的な合併症
狭心症の合併症には、さまざまな病気があります。それらの中でも主な合併症が、以下の3つになります。
不整脈
狭心症や心筋梗塞の発作を経験したことのある方の中には、合併症として不整脈を指摘される例も見られます。
不整脈とは、心臓の拍動リズムが不規則になる症状のこと。脈拍が早くなったり、逆に遅くなったりなど、本来規則的なリズムを打つべき拍動が乱れてしまう症状のことを不整脈と言います。
不整脈には、痛みなどの自覚症状がありません。よって、健康診断などで指摘まで、自分が不整脈であることに気付かない人もいます。
心不全
狭心症や心筋梗塞の患者の多くに、心不全の傾向が見られます。心不全とは、心臓の働きが全体的に弱ってしまう病気のこと。心筋梗塞とは異なり、急に死に至ることはまれですが、長期的には余命を縮める病気と言われています。
狭心症や心筋梗塞、高血圧、不整脈、心筋症、弁膜症など、さまざまな要因によって心不全にいたると言われています。
心不全の予防のためには、肥満の解消や塩分の摂取制限、禁煙など、生活習慣の見直しを図ることがもっとも大事です。
心筋梗塞
狭心症が悪化した状態が心筋梗塞、と考えてください。心臓の冠動脈が狭くなり、血流が悪くなる病気が狭心症。心臓の冠動脈が封鎖されて、血流がほぼ止まってしまう病気が心筋梗塞です。
両者は、病名こそ異なるものの発症メカニズムはとても似ています。ご存知の通り、心筋梗塞は即死を招きかねない恐ろしい病気。一度でも狭心症の発作を起こしたことがある方は、以後、生活習慣の改善や通院などを通じ、少しでも心筋梗塞のリスクを低下させるようにしましょう。
狭心症のリスクを高める要素
狭心症のリスクを高める要素として、以下、代表的な5つのリスク要因を見てみましょう。
動脈硬化
繰り返しますが、狭心症の直接的な原因の大半は動脈硬化です。血管が固くなって弾力が低下したり、血管内におけるコレステロールの蓄積で血管が狭くなったりなどの状態を総称して、動脈硬化と言います。
動脈硬化による血管の狭窄自体が狭心症の直接的な要因にもなりますが、動脈硬化によって生まれた血栓が血管を詰まらせてしまうことも、狭心症の要因となることがあります。
加齢に伴って徐々に進行する動脈硬化ですが、それに加えて、悪しき生活習慣が動脈効果の進行をさらに早めることも知られています。以下に紹介する糖尿病や脂質異常症、高血圧などの生活習慣病は、動脈硬化の進行を早める主な要因。ほかにも、喫煙が動脈硬化に深く関与していることも知られています。
糖尿病
糖尿病とは、血液中のブドウ糖の量(血糖値)が慢性的に多い状態のこと。直接的な原因は、ブドウ糖の吸収を助けるインスリンの分泌量の低下です。
インスリンの分泌量が低下する要因は主に2つ。1つ目がウイルス感染。若い方に多く見られる糖尿病で、医学的には「1型糖尿病」と呼ばれています。2つ目が生活習慣。カロリー過多、運動不足、肥満などが原因でインスリンの分泌量が低下して生じる糖尿病で、医学的には「2型糖尿病」と呼ばれています。
これら1型・2型のうち、糖尿病患者の約95%は2型。すなわち、糖尿病患者の大半が生活習慣を原因としている、ということです。
なお不適切な生活習慣は、糖尿病だけではなく、動脈硬化や脂質異常症、高血圧など、狭心症を誘発する他の症状も招くリスクもあります
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症とは、血液中のコレステロール値や中性脂肪値が、一定の基準よりも高い状態のこと。かつて高脂血症と呼ばれていた症状です。俗に言う「ドロドロ血」とは、脂質異常症の状態にある血液を指しています。
脂質異常症が長く続くと、やがて血液中の余分な脂質が血管に蓄積され、動脈硬化のリスクが上昇。動脈硬化が狭心症や心筋梗塞の最大のリスク要因となることは、すでに説明済みです。
なお動脈硬化は、狭心症や心筋梗塞だけではなく、脳梗塞の主要な要因としても知られる症状。生活習慣を改善させて脂質異常症を予防することは、ひいては、さまざまな病気のリスクを低下させることになることを理解しておきましょう。
高血圧
血液は、心臓によるポンプの圧力によって全身を巡っています。このポンプの圧力が強くなっている状態が高血圧。一般に、上の血圧が140以上、下の血圧が90以上を示した場合、高血圧と診断されます。
心臓のポンプの力が強いということは、その分、血流による血管内壁へのストレスが強いということ。長期的に高血圧の状態が続くことにより、血管が徐々に侵され、やがて動脈硬化を誘発することがあります。
高血圧の主な原因は、肥満、ストレス、喫煙、塩分過多。いずれも生活習慣に関連しているものばかりです。生活習慣に関連している以上、本人の心掛け次第で、高血圧のリスクを低下させることができる、ということでもあります。
高尿酸血症(痛風)
血液中の尿酸値が高い状態が、高尿酸血症。一般に尿酸値が7.0mg/dlを超えた患者は、高尿酸血症と診断されます。
高尿酸血症の状態が長く続くと、血液の中の尿酸が結晶となり関節に沈着。結果、激しい痛みを伴う痛風にいたることもあります。
尿酸値が高い方に多く見られる症状が、メタボリックシンドローム。肥満や脂質異常症、高血圧などを一定水準以上で併発している状態が、メタボリックシンドロームです。やはり高尿酸血症も、その原因には生活習慣が深く関与している、ということです。
高尿酸血症を予防・改善するためには、肥満解消を目指しつつ、プリン体の多い食品の摂取を控えることが大事です。
狭心症に対してわかなつみの発酵菌のはたらきが期待できること

狭心症は血液をサラサラにすることで予防が可能な病気。その点で、わかなつみの発酵菌の酵素活性値は非常に参考になる情報だと考えられます。
鈴鹿医療科学大学での分析結果では、わかなつみの発酵菌の活性値が、他の一般的な酵素サプリに比べて、数十倍もの数値を記録しました。
炭水化物を消化・分解する酵素「アミラーゼ」では約11倍、タンパク質を消化・分解する酵素「プロテアーゼ」では約43倍、脂肪を消化・分解する酵素「リパーゼ」では約19倍もの差です。
このように酵素活性が高いため、日々摂取する食べものを分解・消化させ、血液のドロドロを未然に防ぐ効果を期待できるかもしれません。
狭心症と酵素の関係
酵素は、摂取された食べ物の栄養を消化して吸収、代謝する作用があります。
これらの作用は血液が体の中を流れて、さまざまな臓器や組織を回る過程で行われているもの。血液中に酵素がたくさん存在していればいるほど、消化吸収や代謝の作用が高まって、ドロドロ血の原因となる余分な成分を減らすことができるのです。
さらに酵素は、血液中の老廃物をバラバラにして流れやすくする効果もあるので、血液をサラサラに整えることができます。
狭心症の原因は、血液中のコレステロールといった余分な成分が心臓の入り口の血管を詰まらせてしまうことで起こるため。したがって、酵素を積極的に摂取していれば病気の予防や改善に期待ができるというわけですね。