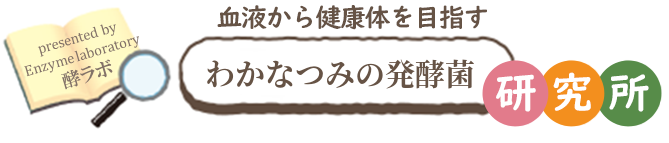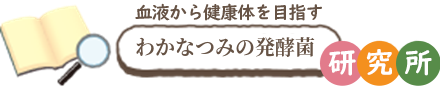健康・長生きのために飲む
「わかなつみの発酵菌」の効果を徹底分析
耳鳴りと酵素の関係性
耳鳴りとは?
耳鳴りは周りの人には聞こえず、「キーン」「ブーン」「ゴー」といった音が聞こえり、感じたりする現象のことを指します。近年は耳鳴りに悩む人が増えているようですが、耳鳴りを病気と捉えず、4割以上の人が治療をしていないのが現状です。
耳鳴りには2種類あります。
- 他覚的耳鳴…体の中に音源があり聴診器を通して他人にも聞こえる
- 自覚的耳鳴…本人にしか聞こえない
耳鳴りに隠された病気とは?
片耳だけに聞こえる
片耳だけの耳鳴りは、突発性難聴、メニエール病、聴神経腫瘍が考えられます。めまいを伴う場合もあるようです。
耳鳴りが両耳から聞こえる
片耳だけでなく、両方の耳から耳鳴りが聞こえる場合には、老人性難聴、騒音性難聴の可能性があります。
老人性難聴は、老化によって引き起こされる難聴です。騒音性難聴は、大きな音が聞こえる場所に長時間いる人が発症することがあるようです。ゲームセンターやコンサート会場で働いている人がなることが多く、職業性疾病とも言われています。
ザーという低音の耳鳴りが聞こえる
耳硬化症(じこうかしょう)耳垢栓塞(じこうせんそく)耳管狭窄(じかんきょうさく)という病気の場合があります。
キーンという金属音の耳鳴りが聞こえる
メニエール病や突発性難聴をはじめ、ストレスなどさまざまな要因で引き起こされている耳鳴りです。
耳鳴りの原因
私たちが音を感じることができるのは「空気の振動」によるもので、外耳、中耳、内耳、神経、大脳の順に送られ、「音」として認識される仕組みです。
このルートのうち、耳鳴りは内耳に異常が生じて起きると言われています。また耳鳴りは「めまい」や「難聴」と同時に発症することが多く、耳鳴りで治療を受けている人の8割は難聴を併発しています。
ストレスや生活習慣と密接な関係がある
「仕事が忙しい」「悩みを抱え解決策がない」など、ストレスを受けやすい環境にあると耳鳴りや難聴になりやすいと言われています。また次のような生活習慣の乱れも、耳に負担をかける原因です。
- 睡眠不足
- ストレス
- 喫煙
- 低血圧
- メタボリック
- 騒音
耳鳴りが酵素不足を警告
私たちの体内には2,000もの酵素があり、栄養成分を吸収したり代謝したりして生命活動を行っています。酵素が不足することにより活動がうまくいかなくなりますが、この危機を知らせてくれるのが耳鳴りやめまいです。
酵素は老廃物の排出にも大きく関わっていますが、酵素不足で排泄が進まず体液が濁ることがあります。濁った体液は耳の周りや首筋などにあるリンパ節にたまるので、耳の器官を乱して難聴や耳鳴りを生じるのです。
耳鳴りは高血圧とも関係性が深い
高血圧は加齢によるものやストレスからくると言われていますが、耳鳴りとも深い関係があります。高血圧が原因で、耳鳴りや頭痛、めまいを患うこともあるため、気になる症状がある方は1週間ほど血圧を測ってみましょう。
日本高血圧学会が発表している「高血圧治療ガイドライン2014」によると、最低血圧が90mmHg以上で最高血圧が140mmHg以上だと病気のリスクが上がると言われています。
高血圧は自覚症状がないことも多く、最悪の場合、命に関わる危険性のある病気です。別名「サイレントキラー」と呼ばれていることから、血圧が高ければ早めに医療機関を受診しましょう。
耳鳴りの予防と対策
ストレスを軽減させる
ストレスは耳鳴りだけじゃなく、さまざまな体の不調を促してしまう可能性があります。仕事が忙しい人や不規則な生活をしている人、悩みを抱えている人は、リラックスする時間を設けてストレスを発散させましょう。
適度な運動
ジョギングや筋肉トレーニングをしなくても、「一駅だけ歩いてみる」「車の利用を減らしウォーキングする」などして運動不足は改善できます。体を動かすことで血行を促進し、固まった筋肉がほぐれます。
積極的に摂りたい食品
次のような食品を多く摂り、耳鳴りを予防しましょう。
- ニンジン・タマネギ・ほうれん草
- 栗やくるみ
- ゴマ
胡麻に含まれる「セサミン」は耳の健康に効果があると言われています。一方で、喫煙やカフェインを含む飲料、添加物が多く含まれる加工食品などは控えた方がいいです。
なんでもバランスが大切です。いろんな種類の食品を少しずつ摂取して、耳鳴りの発症を防ぎましょう。