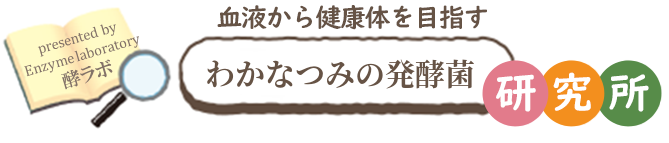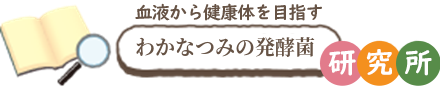健康・長生きのために飲む
「わかなつみの発酵菌」の効果を徹底分析
酵素の歴史とは
酵素の歴史
「酵素」という言葉をよく耳にする機会が増えてきましたが、どのような歴史を持っているのか知っていますか?人間が酵素を活用した歴史は非常に古く、紀元前3000年ごろには利用してきたとの記録が残っています。しかし「酵素」という物質そのものの存在までは把握できておらず、酵素の効果を上手く取り入れていたようです。
物質として最初に発見されるようになるのは1833年で、ジアスターゼ(アミラーゼ)と呼ばれる酵素になります。それ以降、さまざまな酵素が発見され多くの分野で酵素のパワーが活用されてきているのが現状です。
酵素の発見
1833年にA・パヤンとJ・F・ペルソ によって人類初となるジアスターゼ(アミラーゼ)という酵素を発見しました。この酵素を発見した方法は麦芽の無細胞の抽出液によって、でんぷんの糖化を発見。その発見によって細胞がなくても、発酵が進むということを知ることができたそうです。
その後1836年には、T・シュワンによって、胃液中のタンパク質分解酵素であるペプシンが発見されています。この時期の酵素は、生体から抽出されたものの、実体が不明の因子として発見されてきたそうです。
さらにインベルターゼやトリプシン、ラッカーゼ、フィターゼなど数多くの酵素が発見されていきます。1926年にはジェームズ・サムナーによってナタマメウレアーゼの結晶化に成功し、初めて酵素が実体化することができました。
サムナーは発見した酵素のウレアーゼがタンパク質であると実験の結果を踏まえ提唱しましたが、サムナーが当時研究の後進国のアメリカで研究していたため、酵素がタンパク質であるという事実は認められることはありませんでした。その後ジョン・ノースロップとウェンデル・スタンレーによって酵素がタンパク質であることが証明され、それ以降、広く認知されるようになりました。
酵素の発展
1876年になると、ドイツのウィルヘルム・キューネによって「酵素 (enzyme)」という言葉が命名され、酵素という言葉が統一されるようになりました。
しかし19世紀当時、ルイ・パスツールによって、「生命は自然に発生することはなく、細胞が一切ないところでは発酵現象が起こることない」という説が有効とされ、この説が広く信じられていました。この世にある有機物は、細胞のサポートがなければ生成することができないとした生気説が広く信じられており、酵素の作用はただの化学反応にすぎないと考えられていたようです。
当時、酵素は生物から抽出する方法しかなく、微生物と同じように加熱すると失活してしまう性質を持っていました。そのため酵素による現象は、酵素が引き起こしているものなのか、それとも目に見えない細胞が混入したことによって引き起こしているのかを区別することは困難であり証明することができない状況です。
その結果、酵素が生化学反応に影響を及ぼすと言った考えは、すぐには受け入れられずに当時のヨーロッパ学会において、酵素の存在を否定するパスツールらによる生気説派と、酵素の存在を認めるユストゥス・フォン・リービッヒらによる発酵素説派の論争が長い間続きました。
最終結論が出されたのは1896年のエドゥアルト・ブフナーの研究結果です。酵母の無細胞抽出物を使用したアルコール発酵を達成したことで酵素の存在を認めることになりました。つまり酵素の存在がしっかり認知されるようになるまでに、長い年月を要したと言えるでしょう。
酵素の研究が進展
20世紀後半になると、生体分子の分離・分析技術が向上してきます。その結果、生命現象を分子の構造が引き起す機能と理解する「分子生物学」、また細胞内の現象を細胞小器官の機能とそれに付随する生体分子の挙動として理解する「細胞生物学」が成立しました。これらの学問が発展したことによって、さらに酵素の研究が進展するようになります。酵素の機能や性質が酵素や酵素を形成するタンパク質の構造またはコンホメーションの変化によって説明できるようになりました。
酵素の機能が、タンパク質の構造に起因しているものであれば、何らかの酵素に適応する構造を持っており、酵素としての機能を発現できると考えることが可能になっていきます。1986年にはトーマス・チェックらによって、タンパク質以外で初めて酵素の作用を示す物質であるリボザイムを発見。
今酵素のパワーを有効に活用するために、この酵素の構造論と機能論に基づいた人工的な触媒の作用を持った超分子と呼ばれる人工酵素を設計し、開発する研究も進められています。